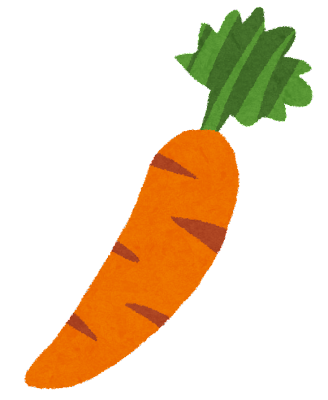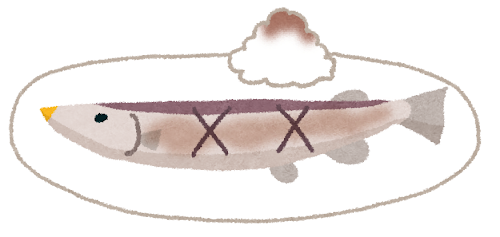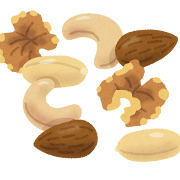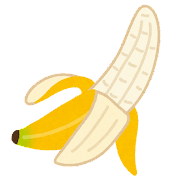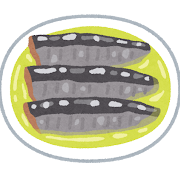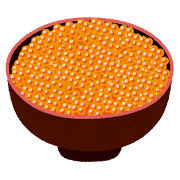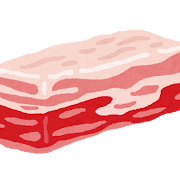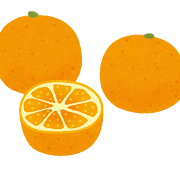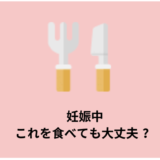この記事では、それぞれのビタミンの効果や働き、それらを多く含む食べ物をご紹介します。
 ぽち
ぽち
 野菜ソムリエ もも
野菜ソムリエ もも
 ぽち
ぽち
目次
ビタミンとは?
ビタミンとは、体の機能を円滑にするのに重要な栄養素です。ビタミンの「VITA」は「生命」という意味で、生命の維持に不可欠な栄養素です。
ほとんどのビタミンは体内でつくることができず、食事などで体の外からとりいれる必要があります。
油に溶けるビタミン・水に溶けるビタミン
ビタミンは脂溶性ビタミンと、水溶性ビタミンに分けられます。ビタミンの種類によって、とるべき調理方法が変わります。
- 脂溶性ビタミン
油に溶けるため、食用油などと炒めると吸収しやすくなります。体に蓄積されやすいので、とりすぎにご注意。 - 水溶性ビタミン
水に溶けるため、茹でる場合はスープなど溶けでた栄養分を食べられるもの、または蒸し料理や炒め料理など、水に溶けでない料理がよいでしょう。とりすぎても尿で排泄されるので、脂溶性ビタミンと比較すると過剰症の危険性は少ないと考えられています。
水溶性ビタミン
 野菜ソムリエ もも
野菜ソムリエ もも
皮膚や目の健康にはビタミンA
ビタミンAは皮膚や目の健康に欠かせないビタミンです。
- 「目のビタミン」といわれており、目の機能に大きく影響します。
不足してしまうと、暗い場所で目が見えづらくなる「夜盲症」や、目が乾きやすくなる「ドライアイ」になることがあります。 - 皮膚や粘膜の正常化・生体の恒常化の維持や細胞の分化に関わります。
皮膚や髪の毛などの細胞を活性化させます。サラサラな髪、ツルツルの肌を保つためには必須です。
また、鼻や喉、肺などの粘膜の材料となり免疫力アップ、風邪予防につながります。
ビタミンAを含む食品
ビタミンAは、「レチノール」と「βカロテン」にわかれます。
レチノールは動物性食品(肉や魚)に多く含まれ、βカロテンは緑黄色野菜に多く含まれます。
| レバー
|
うなぎ
|
卵黄 |
| 人参
|
ほうれん草
|
かぼちゃ
|
骨を丈夫にするにはビタミンD
ビタミンDは、骨を丈夫にするビタミンです。
紫外線に当たることで皮膚で生成されるビタミンです。
- カルシウムの吸収や、骨の形成を促進します。
不足すると、背骨や足の骨が曲がる「くる病」や、「骨軟化症」「骨粗鬆症」にかかりやすくなります。
ビタミンDを多く含む食品
ビタミンDは、きのこ類に含まれるD2と、魚類や卵に含まれるD3にわかれます。
| カレイ
|
うなぎ
|
シイタケ |
| サケ
|
サンマ
|
サバ
|
若返りにはビタミンE
ビタミンEは体の酸化を防ぐビタミンです。
- 「若返りビタミン」といわれており、不飽和脂肪酸の過酸化を抑制します。
酸化は体のサビをイメージするとわかりやすいですが、シミやシワができたり、内臓の老化につながります。 - 生殖や粘膜の正常化に関わります。
皮膚の細胞を活性化させます。ビタミンAと同様に、ツルツルの肌には必要な栄養素です。
また生殖機能を活性化させる働きがあり、不足すると生理障害・更年期障害・生殖機能の衰えなどにつながります。
ビタミンEを多く含む食品
種実類や、大豆油・とうもろこし油などに多く含まれます。
| 胚芽米
|
とうもろこし油
|
大豆油
|
オリーブ
|
| 種実類
|
かぼちゃ
|
アボカド
|
モロヘイヤ
|
血と骨のためにはビタミンK
血液と骨のために働くビタミンです。
- 「止血ビタミン」といわれており、血液を固める働きをします。
不足すると、新生児出血症になったり、血液凝固時間が長くなることがあります。 - 骨の形成にも関わっていて、カルシウムを取り込むサポートをします。
ビタミンKを多く含む食品
納豆などの発酵食品、ひじきや昆布などの海藻類、緑黄色野菜の中でも青菜(ほうれん草など)に多く含まれています。
| 納豆
|
昆布
|
わかめ
|
海苔
|
| ほうれん草
|
小松菜
|
モロヘイヤ
|
キャベツ
|
脂溶性ビタミン
 野菜ソムリエ もも
野菜ソムリエ もも
疲労回復にはビタミンB1
ビタミンB1は、エネルギーと糖質の代謝に関わるビタミンです。
- エネルギーの代謝を助け、疲労回復に役立ちます。疲れの原因となる乳酸を分解し、エネルギーに変えるサポートをします。
- 糖質をエネルギーに変え、糖質が脂肪になることを防ぎます。
不足すると、糖質がエネルギーに変わらないため、食欲不振や倦怠感を感じやすくなります。
さらに不足すると、脚気や、多発性神経症になってしまいます。
ビタミンB1を多く含む食品
豚肉、枝豆などの豆類、種実類に多く含まれます。
| 豚肉
|
枝豆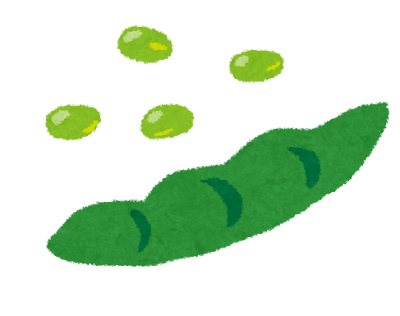 |
あずき |
| 大豆
|
豆腐
|
種実類
|
ダイエットにはビタミンB2
ビタミンB2は、三大栄養素である脂質・糖質・タンパク質の代謝に関わるビタミンです。
- 脂質・糖質・タンパク質の代謝を促し、エネルギーに変えてくれるので、脂肪を溜め込むことを防ぎます。ダイエットの際は積極的にとるとよいでしょう。
- 細胞の再生と成長を助ける役割があります。不足すると細胞の成長が滞り、成長障害を引き起こします。また、細胞の再生が滞ると、口内炎・口唇炎・舌炎などの原因にもなります。
ビタミンB2を多く含む食品
レバー、牛乳、卵類に多く含まれます。
| レバー
|
牛乳
|
卵類
|
魚肉ソーセージ
|
| 海苔
|
わかめ
|
缶詰(水煮)
|
アーモンド
|
代謝アップにはナイアシン
ナイアシンは、糖質や脂質を燃やしてエネルギーに変えるときに必要なビタミンです。
- 脂質・糖質・タンパク質の代謝を促し、エネルギーに変える働きをします。体を動かしたり、内臓が働くためにはエネルギーが必要なので、ナイアシンは日々の活動に必須のビタミンといえるでしょう。不足すると、皮膚,粘膜,中枢神経系,および消化管の症状を特徴とするペラグラという病気にかかってしまいます。先進国では稀ですが、インドや中南米などで発生している病気です。
ナイアシンを多く含む食品
| レバー
|
カツオ
|
マグロ
|
落花生
|
お肉好きには欠かせないビタミンB6
ビタミンB6は、タンパク質からエネルギーを生み出したり、血液や筋肉をつくるのを手助けをするビタミンです。
- タンパク質をアミノ酸に分解したり、別のアミノ酸を合成します。
ビタミンB6を多く含む食品
カツオやマグロなどの魚類や、緑黄色野菜に多く含まれます。
レバー |
カツオ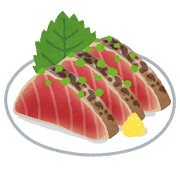 |
マグロ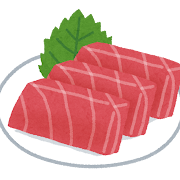 |
| バナナ
|
人参
|
かぼちゃ
|
貧血予防にビタミンB12
ビタミンB12は、タンパク質や核酸、赤血球の生成に関わるビタミンです。
- “赤いビタミン”といわれ、赤血球を合成します。不足すると、悪性の貧血にかかってしまいます。
またタンパク質や核酸の生成に関わり、免疫システムを元気にする役割を果たしています。 - 全身をコントロールする中枢神経や、全身に張り巡らされた末梢神経をコントロールしています。不足すると神経障害を引き起こします。
ビタミンB12を多く含む食品
野菜にはあまり含まれず、卵・肉(レバー含む)・魚介類などの動物性食品に多く含まれます。
レバー |
卵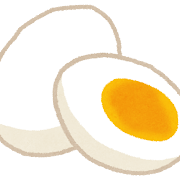 |
イワシ
|
| アサリ
|
いくら
|
たらこ
|
代謝アップでダイエット効果のあるパントテン酸
パントテン酸は、糖質や脂質の代謝に関わるビタミンです。
- 糖質・脂質の代謝に関わり、エネルギーに変える働きをします。脂質が体内に蓄積されるのを防ぐので、ダイエットの味方となるビタミンです。不足すると、成長障害、体重減少、めまいなどを引き起こす可能性があります。
パントテン酸を多く含む食品
“パントテン”はギリシャ語で「どこにでもある」という意味です、その語源の通り、様々な食品に含まれていますが、特に含有量が多いのはレバー・肉類・卵です。
レバー |
卵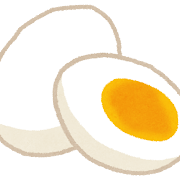 |
納豆
|
| 鶏肉
|
豚肉
|
たらこ
|
エネルギー代謝と美容にはビオチン
ビオチンは、三大栄養素をエネルギーに変えるサポートをするビタミンです。
- ビオチンは、「ビタミンH」ともいわれます。Hはドイツ語の「肌」という意味の”haut”の頭文字。皮膚の働きを活性化させたり、髪や爪の健康を保つ働きをします。ハリのある肌、ツヤのある髪を維持するために必要な栄養素です。不足すると皮膚炎や脱毛などが起こります。
- 三大栄養素である脂質の合成、糖質やタンパク質の代謝に関わっています。不足すると倦怠感や神経障害を引き起こすことがあります。
ビオチンを多く含む食品
レバー、卵黄、緑黄色野菜などに多く含まれます。腸内細菌で体内でも作られています。
レバー |
卵黄 |
うなぎ
|
| モロヘイヤ
|
人参
|
小松菜
|
成長や妊娠の維持には葉酸
葉酸は、ビタミンです。
- タンパク質などを作る際に必要なDNAの合成や細胞分裂に重要な役割を果たします。そのため、成長・妊娠(胎児の発育)の維持に必要なビタミンです。妊娠期に不足すると胎児の神経管閉鎖障害を招きます。また赤血球の細胞の形成を促進する働きもあり、不足すると巨赤芽球性(きょせきがきゅうせい)貧血を引き起こすことがあります。
葉酸を多く含む食品
レバー、胚芽、卵、緑色野菜に含まれます。植物の緑の葉の部分に多く含まれます。
レバー |
卵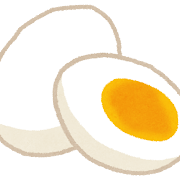 |
胚芽米
|
| 枝豆
|
モロヘイヤ
|
アボカド
|
免疫力アップにはビタミンC
ビタミンCは、免疫力を高め、美肌を保つ働きをするビタミンです。
- アミノ酸の代謝を助け(アミノ酸が細胞をつくったり、酵素やホルモンの材料となって働くのを側面からサポート)、免疫力アップや老化防止に役立ちます。
- コラーゲンの生成と保持で、肌をツヤツヤにする働きがあります。また骨の細胞もコラーゲンでできており、骨粗鬆症を防ぐ役割もあります。不足すると組織間をつなぐコラーゲンの生成と保持に障害を受け、血管への損傷により壊血病を引き起こすことがあります。
- 活性酸素の働きを抑える抗酸化作用があり、免疫力を高める働きがあります。活性酸素が増えすぎると、細胞の機能が低下し、ガンや動脈硬化、糖尿病などの原因となります。
ビタミンCを多く含む食品
ビタミンCは、柑橘類・イチゴ、緑黄色野菜・ニガウリなどに多く含まれます。リンゴやバナナなどは含まれるビタミンCは多くなく、全てのフルーツにビタミンCが多く含まれているわけではありません。コラーゲンの生成を助けるタンパク質も一緒にとるようにすると効果的です。
パプリカ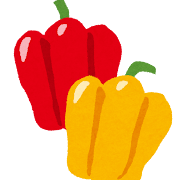 |
ブロッコリー |
キウイ
|
| いちご
|
みかん
|
にがうり
|
まとめ
 ぽち
ぽち
 野菜ソムリエ もも
野菜ソムリエ もも
 ぽち
ぽち